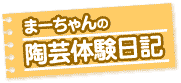
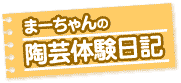 |
| 第七回(平成14年9月7日) | ||
| <LESSON15―施釉、絵付け(3)―> いよいよ、施釉に挑戦します。テストピースを見て、どんな仕上がりの色になるのか確かめて、好みの釉薬をかけます。
|
||
 |
7.釉薬をかきまぜる 釉薬は使うたびにしっかりかき混ぜてから使用します。少しの時間でも、成分が沈殿してしまうので、要注意です。 |
|
 |
8.飴釉をかける 今回まーちゃんは湯呑みを、先生のアドバイスをもとに朝鮮唐津風※の仕上がりにすることに!まず器の外側だけにひしゃくを使って飴釉をかけます。 ※朝鮮唐津についてはこちら→ |
|
 |
施釉するときは、器の底に釉薬がつかないようにしましょう。釉薬が底についていると、焼成時に釉薬が流れ出し、底が張り付いてしまうことになります。万一釉薬がついた場合は、水で固く絞ったスポンジを使ってしっかり釉薬をふきとっておきます。 |
|
 |
9.藁灰釉をかける 次に器の内部に藁灰釉を入れてまんべんなくいきわたるようにします。そして口の外側に少し藁灰釉がつくように釉薬のバケツに、作品を直接つっ込みます。静かに引き戻して、自分の気にいった流れができていればできあがり。 |
|
 |
10.できあがり! 写真の茶色っぽいところが飴釉で、焼成すると黒っぽい仕上がり。灰色の部分が藁灰釉で、焼成すると白っぽい仕上がりになります。また焼成時に藁灰釉が流れだしおもしろい効果が期待できます。 |
|
 |
11.マグカップも施釉 まーちゃんはマグカップにも施釉。これは藁灰釉を全体にかけた後、部分的に緑釉をかけました。写真の薄い灰色部分が藁灰釉薬、濃い灰色部分が緑釉です。 ※先生による釉薬かけの動画はこちら→ |
|
| LESSON15―施釉、絵付け(4)に続く | ||