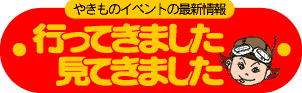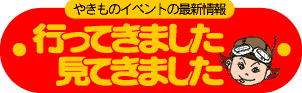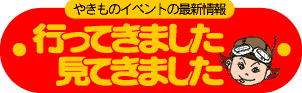
■石橋美術館別館常設展示第7期
工芸の美―漆器と陶磁器
<会期:平成13年3月6日〜4月22日> |
平成13年4月13日 |
 九州北部では桜の木が、ピンクから若葉色に変わろうとしています。本日おじゃました石橋美術館別館は、石橋美術館に隣接しています。この別館は石橋コレクションのなかの日本書画や陶磁器類を展示するために、5年程前に開館したそうです。今回鑑賞してきたのは2000年度常設展示の第7期「工芸の美―漆器と陶磁器」です。陶磁器は漢代から清代にかけての中国古陶磁を約20点、漆器は江戸時代から近代にかけての作品が展示されていました。学芸員の平間さんのお話を伺いながら鑑賞させていただきました。 九州北部では桜の木が、ピンクから若葉色に変わろうとしています。本日おじゃました石橋美術館別館は、石橋美術館に隣接しています。この別館は石橋コレクションのなかの日本書画や陶磁器類を展示するために、5年程前に開館したそうです。今回鑑賞してきたのは2000年度常設展示の第7期「工芸の美―漆器と陶磁器」です。陶磁器は漢代から清代にかけての中国古陶磁を約20点、漆器は江戸時代から近代にかけての作品が展示されていました。学芸員の平間さんのお話を伺いながら鑑賞させていただきました。
 作品は見やすく時代順に展示されてあり、各時代のポイントを掴みながら見ることができました。漢時代の作品は灰釉や緑釉といったどちらかというと地味な感じの作品ですが、次の唐時代の作品は華やかで雰囲気が一変していました。「唐時代ではシルクロードによる文化交流も盛んになってきますので、中国陶磁も西国の影響を受けたものと思われます。こちらの作品は文様がペルシャ風になっていますね。」と平間さんが紹介してくれたのは「三彩宝相華文三足盤」です。クリーム色の地肌に緑、黄、青で文様が描かれています。 作品は見やすく時代順に展示されてあり、各時代のポイントを掴みながら見ることができました。漢時代の作品は灰釉や緑釉といったどちらかというと地味な感じの作品ですが、次の唐時代の作品は華やかで雰囲気が一変していました。「唐時代ではシルクロードによる文化交流も盛んになってきますので、中国陶磁も西国の影響を受けたものと思われます。こちらの作品は文様がペルシャ風になっていますね。」と平間さんが紹介してくれたのは「三彩宝相華文三足盤」です。クリーム色の地肌に緑、黄、青で文様が描かれています。 文様はまさにペルシャ絨毯を思い出すようなもので、なめらかな曲線をしっかりとした線で縁取られています。この縁取りで一層、文様の色が引き立っています。磁器が登場する前には、釉薬の発色を良くするために白化粧を施した後に、このような鮮やかな色絵を施していたそうです。また、唐時代には磁器も登場します。「白磁龍耳壺」は龍をかたどった耳が特徴です。龍といえば恐ろしい印象ですが、この作品では壺の口に頭をつっこんでいるところが、愛嬌があり思わずこちらも壺の中を覗いてみたくなります。龍は中国では不思議な力があるとされ、動物の頂点を意味していました。 文様はまさにペルシャ絨毯を思い出すようなもので、なめらかな曲線をしっかりとした線で縁取られています。この縁取りで一層、文様の色が引き立っています。磁器が登場する前には、釉薬の発色を良くするために白化粧を施した後に、このような鮮やかな色絵を施していたそうです。また、唐時代には磁器も登場します。「白磁龍耳壺」は龍をかたどった耳が特徴です。龍といえば恐ろしい印象ですが、この作品では壺の口に頭をつっこんでいるところが、愛嬌があり思わずこちらも壺の中を覗いてみたくなります。龍は中国では不思議な力があるとされ、動物の頂点を意味していました。
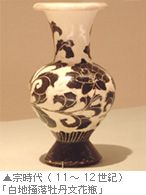 宋時代の「白地黒掻落牡丹文瓶」は白と黒というモノトーンの作品ですがとても華やかさを感じます。その形と色の配分のせいか、ドレスを着た貴婦人を連想させます。 宋時代の「白地黒掻落牡丹文瓶」は白と黒というモノトーンの作品ですがとても華やかさを感じます。その形と色の配分のせいか、ドレスを着た貴婦人を連想させます。 どうやって制作したのか平間さんにお尋ねしました。「これは、成形した土の上に白化粧を施した後、全体に黒絵具をかけています。乾燥させた後に黒絵具の部分を掻き落として文様を作り出し、最後に透明釉がかけられています。」平間さんの説明で制作方法がわかると、ますます細かいところまで見たくなります。 どうやって制作したのか平間さんにお尋ねしました。「これは、成形した土の上に白化粧を施した後、全体に黒絵具をかけています。乾燥させた後に黒絵具の部分を掻き落として文様を作り出し、最後に透明釉がかけられています。」平間さんの説明で制作方法がわかると、ますます細かいところまで見たくなります。
その隣には中国古陶磁といえば思い浮かぶ、青磁の作品がありました。「青磁長頸花」はその色の清々しさと、無駄のないフォルムが高貴さを感じさせます。
 明時代になると赤絵が発達し、その技法は日本の磁器生産にも影響を与えます。「呉須赤絵花鳥文大皿」は一尺(約30cm)を越える大皿です。見込み(皿の中央)部分には池で遊ぶ水禽が生き生きと描かれており、その周囲には花鳥文や格子文が描かれています。 明時代になると赤絵が発達し、その技法は日本の磁器生産にも影響を与えます。「呉須赤絵花鳥文大皿」は一尺(約30cm)を越える大皿です。見込み(皿の中央)部分には池で遊ぶ水禽が生き生きと描かれており、その周囲には花鳥文や格子文が描かれています。 線に勢いがあるので躍動感が感じられ、細かな文様にもかかわらず大胆さも兼ね備えた作品です。呉須赤絵は白磁の素地や、染付素地に赤、緑、青などの釉で文様を奔放に絵付けしたのが特徴で、この作品はその中でも代表的なものなのだそうです。 線に勢いがあるので躍動感が感じられ、細かな文様にもかかわらず大胆さも兼ね備えた作品です。呉須赤絵は白磁の素地や、染付素地に赤、緑、青などの釉で文様を奔放に絵付けしたのが特徴で、この作品はその中でも代表的なものなのだそうです。
清時代のコーナーにはユニークな作品が並んでいました。「辰砂象耳角形花瓶」は特に清時代を代表する作品ではないそうですが、18〜19世紀にかけての作品で、耳の部分がなんと象の頭になっています。結構手の込んだつくりになっていて、シンプルな形の瓶に強烈なアクセントをつけています。
歴史の長い中国の作品ですので、陶磁器の技法の歴史も辿ることができ、中国における作品のバラエティさを味わえました。今回の常設展は中国古陶磁の作品でしたが、日本の近代陶芸などを展示する会期もあるそうです。また月に一度学芸員の方による。展示作品や作家解説なども行われているそうです。
|
■予告
石橋美術館別館では、先ごろブリヂストン美術館で行われた「オリエントのガラスと陶器」展が4月27日から7月8日に開催予定です。土器、ガラス、陶器の作品で先史時代から20世紀初頭までを見ることができるそうです。
|
●石橋美術館別館
【所在地】福岡県久留米市野中町1015
【電 話】 0942-39-0124
【駐車場】有
【休館日】月曜日
|