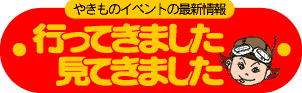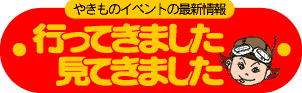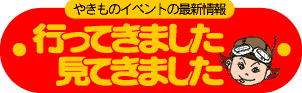
小野琥山・小野珀子 回顧展
<会期:平成18年9月16日〜24日>
|
| 平成18年9月16日 |
|
一雨ごとに涼しくなる今日この頃。佐賀平野では稲刈り間近の稲穂が秋雨に穂をぬらしています。そんな雨の一日、佐賀県立九州陶磁文化館へ出かけ、「小野琥山・小野珀子 回顧展」におじゃましました。
この回顧展は、釉裏金彩(ゆうりきんさい)とよばれる技法で佐賀県重要無形文化財になった小野珀子(1915〜96)、また現在の嬉野市に琥山製陶所を作ったその父・小野琥山(1890〜1971)の二人の作品、約105点を紹介するものです。
琥山没後35年、珀子没以後10年という節目を迎えた今年、小野琥山・小野珀子父娘の作陶の歴史をたどり、その業績を広く知ってもらおうと開催されているものです。
小野琥山は福島県に生まれ、名古屋の日本陶器(現在のノリタケ)に就職し、ヨーロッパの美術工芸品に感銘をうけます。その後、現在の嬉野市に琥山製陶所をつくり、自身の作陶生活のかたわら、後進の育成に努めます。
琥山製陶所からは多くの陶芸家が輩出されたことから、琥山製陶所は「琥山学校」と呼ばれるほどになります。小野琥山は、堆白手(ついはくで)という独特の技法を考案しつつも、その作品はほとんどが未発表だったそう。
 |
| ▲小野珀子の作品 |
小野琥山の娘・小野珀子は琥山窯でデザイン・絵付けに従事。人間国宝・陶芸作家の加藤土師萌氏の金彩技法に感動し、試行錯誤の研究を重ね、珀子ならではの釉裏金彩を完成させます。その繊細で艶やかな釉裏金彩技法の作品は、多くの人々を魅了し、平成4年に佐賀県重要無形文化財に指定されます。
小野琥山の「堆白手」、小野珀子の「釉裏金彩」。このふたつの技法はどんなものだったのか、展示作品とともにご紹介いたします。
小野琥山の「堆白手(ついはくで)」は日本で彼が初めて考案した技法とのこと。明治42年頃、日本陶器に在職中に考案。その後も研究を続け、1921年には名古屋製陶所(現在の鳴海製陶)より、この堆白手の作品を化学工業大博覧会に出品し、総裁賞を受けています。
 |
| ▲青地堆白手水仙文花入 |
展示作品「青地堆白手水仙文花入」は、彼の堆白手技法作品の中でも代表作となっているものです。青緑色の深くしっとりとしたバックに、淡く水彩画のように浮かびあがる水仙の花が印象的です。
堆白手はまず、天草陶土と呉須を混ぜた泥しょうを、成形した陶土の表面にまんべくなく塗ります。これが深い青緑色の部分になります。これをよく乾燥させた後、天草陶土の泥しょうを薄めたものを絵具のように用いて何度も塗り重ねながら、花文様を描いていきます。その後、白磁の釉薬をかけて本焼きを行う…というのが堆白手の基本的な流れです。
 |
| ▲飴釉堆白手薔薇文合子 |
陶土と呉須を混ぜたものを用いるため、絵具だけとは一味違う深みのある色合いが、作品の表面を彩ります。また同じく陶土で文様を表現しますので、立体感を感じられる独特の文様が浮かびあがるように、見る人に迫ってきます。
同じく堆白手を用いた作品「飴釉堆白手薔薇文合子」は、先の呉須のかわりに飴釉を用いたものです。しっとりした光沢と深みのある透明感はまるで「べっこう」を思わせます。
 |
| ▲釉裏金彩花壺『煌』 |
次に小野珀子の「釉裏金彩(ゆうりきんさい)」をご紹介しましょう。成形後、本焼きまですませた磁胎に地色を施して焼成します。焼きあがった表面に次は均一に漆を塗ります。
漆が乾かないうちに、金箔を貼り付け文様をつくっていきます。漆は接着剤の役割をはたしているんですね。その上から釉薬を塗り焼成。さらに上釉をかけて焼成。
これにより透明感のある釉薬の中に金箔で施された文様が浮かび上がってきます。
彼女の代表作、「釉裏金彩花壺『煌』」もこういった技法を用いたもの。非常に薄い金箔を用いることから、根気のいる仕事であったろうと想像されますが、あでやかで神々しささえ感じる「輝く」技法の作品は、長時間見ていてもつい引き込まれてしまうような憧れに近い感覚をおぼえます。宝石や金銀など輝くものに、心奪われる心理と同じものなのかもしれません。
 |
| ▲赤字金襴手葡萄文壺 |
同じく小野珀子の「赤字金襴手葡萄文壺」も、金彩技法を用いたものです。赤と金色の対比が美しく、エキゾチックな雰囲気の作品です。こちらは文様となる部分に漆を塗り、その上から金箔をおします。そして葉の葉脈などは尖った道具を用いて金箔をそぎ取りながら文様に仕上げています。また最後の上釉は施されていませんので、金箔の光沢感を直接感じることができます。
独特の技法の研究に時間を費やし、手間隙をおしまず独自の美の世界を追求した小野琥山・小野珀子父娘の足跡を振り返る展覧会。作家の制作活動に対する情熱のようなものを感じることが出来たと同時に、陶磁器における表現技法の幅広さを改めて知ることができた展覧会でした。
今回この展覧会を記念して、「天空の黄金 小野珀子と釉裏金彩」※も発刊され、より深く小野珀子の作陶活動を知ることができます。
陶芸作家が多い佐賀ですが、なかなか目立った活動をしている女性作家は少ないのが現状です。小野珀子に続くような女性作家、また独自の美の世界を創造してくれる若い作家さんが登場してくれるのを期待しつつ、会場をあとにしました。
■ 取材雑記 ※
「天空の黄金 小野珀子と釉裏金彩」
著者:小野ゑみ
発行所:株式会社コエランス
定価:3,150円(税込)
口絵 小野珀子作品カラーページ8枚つき
●佐賀県立九州陶磁文化館
【所在地】西松浦郡有田町戸杓乙3100-1
【電 話】0955-43-3681
【駐車場】有
【休館日】月曜日・12/29〜12/31
|
|
|