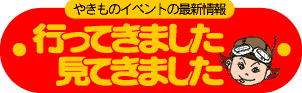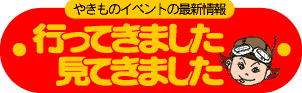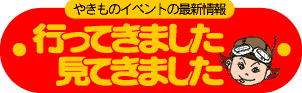
やきもののかたち 人と動物
<会期:7月23日(水)〜8月31日(日)>
|
| 平成20年7月29日 |
|
 毎日暑い日が続いています。 毎日暑い日が続いています。
今回は佐賀県立九州陶磁文化館で開催されている夏休み特別企画「やきもののかたち 人と動物」展へおじゃましました。やきものというと食器のイメージが強いかと思われますが、肥前地方の陶磁器では観賞用の人形類も多くつくられています。その製作は古伊万里など江戸時代から多くみられ、人型はもちろん動物なども多種にわたりつくられ、工芸品としても高く評価されているそうです。
今回の展覧会では、この人形類にスポットをあて、その製法や意匠を紹介。29件86点の作品や資料がならび、「(1)やきものの人形の内部を見てみよう!」・「(2)やきものの人形はどうやってつくるの?」・「(3)さまざまな人物像」・「(4)やきものの動物園」と4つのコーナーで紹介されています。
会場へ入るとなにやら、いつもの展覧会とは様子が違います。壁にはレントゲンのようなパネルが並んでいますが…。「(1)やきものの人形の内部を見てみよう!」では、普段はその外観しか見ることができないやきものの人形を、最新の文化財用X線CTスキャンで撮影した様子を公開。人形の内部構造をCTスキャンの写真パネルで見ることができます。
 |
| ▲「色絵婦人像(柿右衛門様式)」 右はそのCTスキャン画像 |
まずは古伊万里人形としてよく知られている「色絵婦人像(柿右衛門様式)」の内部構造を見ていきましょう。この人形の内部写真は九州国立博物館の文化財用CTスキャンで撮影。今回のこの撮影によって「色絵婦人像」が絶妙なバランスによって成形されていることがわかりました。パネル写真を参考に御覧ください。やきものは焼成すると、大きさがが縮みます。また焼成中には土の重さによってへたってくるという製作上の難点があります。またこのへたり具合は、使用される土の成分によっても変わってくるので、いかに焼成後のできあがりを計算して成形するかが、職人技のみせどころのひとつともなります。
「色絵婦人像」を正面からみた断面からは、まず首元の襟部分が周囲より厚めにつくられていることが分かります。これは頭の重みを支えるためにあえて厚めに仕上げているのです。
そして肩部分には空気穴がありました。これは焼成時に内部の空気が膨張して人形を破損しないようにつくられた、いわば空気の逃げ道です。この空気穴は人形の髷部、口にもあり、細かい形に細工されている頭部も上手に空気が抜けるようになっていました。
そして女性らしく胸元に手をそえた左腕の袖部分。この袖の上部は他の場所と比べるとたいへん薄くなっています。ここに重みがでると袖部分がへたってしまうからだと考えられます。微妙な厚みの調整で、「色絵婦人像」の優雅でたおやかなポーズが表現されているのです。また腰から足にかけては均一な厚みで仕上がっています。これは胴体の上部を支えるとともに、焼成時のゆがみを防いでいるのです。
この他にも頭部を横から、また胴体を横から撮影したCT画像もあり、この人形の内部の全体像を見ることができます。
 |
| ▲婦人像土型 |
さてこのように随所に工夫がこらされた人形は、一体どうやってつくられるのでしょうか?
「(2)やきものの人形はどうやってつくるの?」では、江戸時代の人形製作工程を復元した研究パネルなどが並びます。それによると、やきものの人形づくりは、まず原型(元型)づくりからはじまります。そしてこの原型をもとに、型を作成。この型をもとに人形をつくります。型の内側に板状にした土を指で押し当てていきますが、その時の厚み加減などは先の「色絵婦人像」で紹介したように、人形の部位によって厚みを工夫しながらつくっていきます。これはかなり手間のかかる仕事で、職人の技と勘の見せ所ともいえるでしょう。
 |
| ▲色絵壺持ち婦人像 |
写真の「婦人像土型」は有田町内の赤絵町遺跡から出土したもの。これは人形の頭部・顔・胴体の前後の土型です。この土型からは、婦人像を胴体の前後で貼り合わせ、手などは別のパーツとしてつくり最後に接合して像を完成させていたことがわかります。
この土型によく似た婦人像も一緒に展示されていました。写真の「色絵壺持ち婦人像」です。左手に壺を持ち、右足を前に出した動きのある姿です。
このできあがりと発掘された土型をあわせて研究することで、製作技法・年代などもわかってくるようです。
最新のCTスキャンだけではなくこのような遺物からも人形のつくりを読み取ることができるのです。
三番目のコーナー「(3)さまざまな人物像」へすすみましょう。江戸時代の有田ではさまざまな人物をモデルに人形がつくられました。これらは装飾品として好まれましたが、特にヨーロッパへの輸出品として人気を博していたのだそうです。
ここでは中国の仙人や歴史上の人物などを人形にしたものが並びますが、私が注目したのは、またまた婦人像。「色絵枝垂桜菊垣文婦人像」・「色絵菊花流水文婦人像」の二体を御覧ください。
「色絵枝垂桜菊垣婦人像」は1700〜50年代、「色絵流水婦人像」は18世紀後半から19世紀前半のもの。
 |
| ▲色絵枝垂桜菊垣文婦人像 ・ 色絵菊花流水文婦人像 |
婦人像は美しさや先にあげたような製法を知るだけではなく、人形がつくられたその当時の風俗も知ることができるのです。色絵婦人像は人気があったようで、江戸時代全般をつうじてつくられていました。
1670年代から1690年代には柿右衛門様式の優美な雰囲気の像。その後の元禄時代(1688〜1704年)や、18世紀のものを見ると、着物や髪型などが次第に変わってきています。また像の表情もずいぶんと違う印象に変化しています。こういった人形の意匠やつくりを見ることで、当時流行していたファッションや髪型などの風俗をうかがい知ることもできるのです。
 |
| ▲色絵狛犬 |
さて最後のコーナー「(4)やきものの動物園」では、人型ではなく動物を模した人形を集めています。動物のなかでも特に多く製作されたのが獅子(狛犬)だそう。人々が願いを込めて二対の狛犬を奉納するという習慣があったので盛んに製作されていたのでしょう。もともとは仏像の前に獅子の像を置くという習慣が、中国から朝鮮半島を経て日本に伝わったものだとか。
写真の「色絵狛犬」は1680〜1700年代のもので、狛犬としては珍しく一対で奉納されていました。佐賀市の伊勢神社に奉納されいたもので、犬の胸には「元禄十三年(1700)」、「井上□□衛門善忠」(□は不明)と奉納年と奉納者が記されています。一対で現存する大型の狛犬としては唯一のものだそうで、貴重な資料とのこと。
力強い眉と大きくあけた口。かっと見開いた目に大きな鼻穴からは、強くて凛々しい雰囲気が伝わりますが、その一方からだに施されたカラフルな水玉模様からは愛らしい雰囲気もただよい、なんだか憎めない表情の狛犬です。
 |
| ▲色絵唐獅子置物 |
もうひとつ狛犬をご紹介しましょう。「色絵唐獅子置物」は1670〜1690年代のもので、柿右衛門様式に属します。美しい磁肌に青色をベースに絵付けされた文様は、優雅な雰囲気。台座には金属製の細工も施されていますので、ヨーロッパへの輸出品だったのかもしれません。
ヨーロッパでは壺などの装飾品を二対並べて飾っていたので、このように二対セットの狛犬も好まれていたのかもしれませんね。
この他にもさまざまな人形のCTスキャン画像や、動物をかたどった近代のノベルティ商品・ミクロスなども並び、ざまざまな角度からやきものの人形にせまることができます。とくにCTスキャン画像は一風かわった展示で、人形製法を視覚的に理解することができます。食器とはひとあじ違うやきものの世界を鑑賞いただけます。
●佐賀県立九州陶磁文化館
【所在地】西松浦郡有田町戸杓乙3100-1
【電 話】0955-43-3681
【駐車場】有
【休館日】月曜日・12/29〜12/31
|
|
|